乳幼児が発熱した際には受診や対応について迷う方が多いと思います
「発熱したら薬を飲ませる」というのは正しいようで間違っています
この記事では受診する目安や発熱時の家での対応について解説していきます
乳幼児の発熱に親が抱く不安
発熱は、子どもが体調を崩した時に最もよく見られる症状の一つです
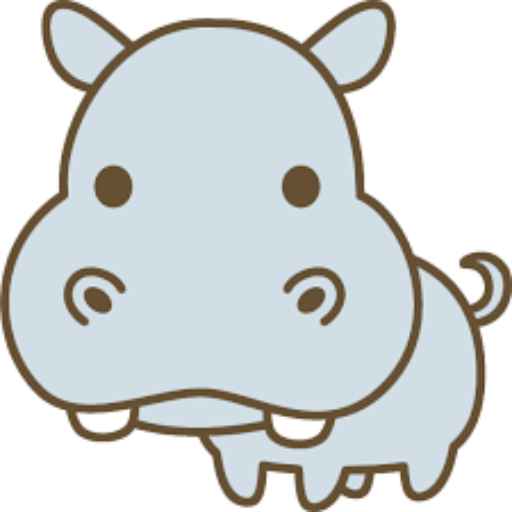
子どもの発熱は心配の種だよね!
子どもは、その年齢が幼いほど、自分の体調や状態を言葉によって的確に説明することが難しいといった特徴があります
そのため、養育者にとって体温は数値としてわかりやすく、子どもの体調を判断する材料となりやすいのです
その一方で、体温の値次第で、「どのくらいまで熱が上がるのか」「いつまで熱が続くのか」といった不安も抱きやすいです
発熱への対応の現状
こうした養育者が抱く発熱に対する不安については、ほとんどの母親(92%)が39度未満の発熱を高熱と捉え、約半数の母親46%が38度未満の発熱でさえ恐怖感を抱いていると報告されています
同様に「37.5度〜37.9度」で病院を受診しようとする人が最も多く(37.9%)子どもが熱を出した時の気持ちを聞いたところ、「どれくらいまで熱が上がるのか心配になる」(58.2%)「いつまで熱が続くのか心配になる」(57%)と答えていました
発熱への誤解
この様な背景には、「発熱=有害なもの・発熱自体が熱生痙攣や脳障害を引き起こす」など発熱に関する知識の誤解が多いです
最近ではインターネットが普及し、様々な育児に関する情報をはじめ、病気に関しても簡単に調べることができます
しかし、いろいろな情報が得られる反面、情報が多すぎて、それらの情報と自分の子どもの症状を照らし合わせて考えることが難しく、かえって不安を募らせてしまうということも生じています
発熱の種類
発熱は2つのパターンに大別されます
1つは「環境の変化によるもの」、もう一つは「体の防御反応によるもの」です
環境の変化
代表格には熱中症があります
周囲の温度が高すぎて体内の熱が放散しきれず体温が上がっていきます
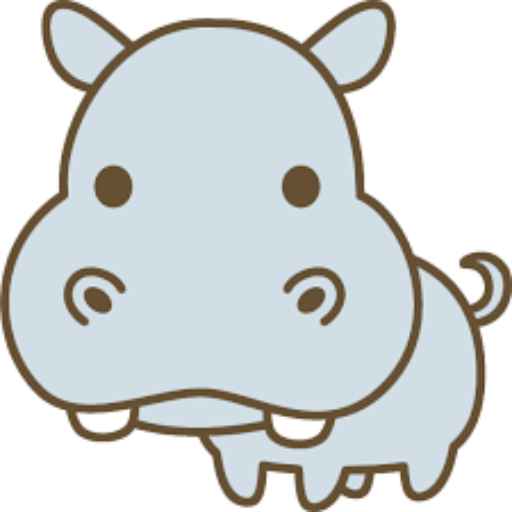
子どもでは暑い時期に車中に置き去りにされることでも起こりやすく注意が必要!
体の防御反応
代表格はは感染症です
体内にウイルスや細菌が侵入してくると免疫細胞の一つである食細胞が反応してサイトカインなどの生理活性物質を作ります。
それらは「プロスタグランジンE2」の産生を促し、この物質が脳に情報を伝え、脳の視床下部にある「体温調節中枢」が体の各部位に体温を上げる様指令を出します
ウイルスは低温の方が繁殖しやすく、体温が上がると増殖が抑制されます
発熱は免疫を強化
発熱により体を守る仕組み(免疫)が活性化されます
小学校に上がる頃までよく熱を出しますが、子どもにとって発熱とは病的な症状ではなく免疫機能を強化する重要な反応となっているのです
乳幼児の発熱原因の大半は感染症によるものです。
新生児期は胎盤を通して母親から獲得した免疫グロブリンによって感染症にかかりにくいことがわかっていますが、この母体由来の免疫は3〜6か月頃にはほとんどなくなります
数年前までは肺炎や髄膜炎を起こす乳幼児が見られましたが、Hibワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの普及により、だいぶ減っています

予防接種はきちんとスケジュールに沿って受けておくことが大切だね!
熱だけで受診を判断しない
子どもは体重に比較して体表面積が広いので環境の影響を受けやすく、成長過程にあるため代謝も非常に活発で体温は高めです
乳幼児の平熱は36.5〜37.5度

38度を超えたら、発熱として何らかの対処をしよう!
ただし、受診するかは熱だけでなく随伴症状をしっかり確認して判断していただきたいです
熱がなくても以下の症状が出現したら注意が必要です
・ぐったり
・目がとろとろ
・母乳やミルクの飲みが悪い
・あやしても全然泣き止まない
・泣き方がおかしい
・嘔吐が止まらない
・ひきつけを起こした
・顔色や口唇の色が悪い
・はあはあと肩で息をする

発熱に関わりなく、いつもと様子が違うと感じたら小児科を受診しよう!
発熱に注意が必要な子
生後3か月未満の乳児で38度の発熱があった場合は、機嫌良くしていても必ず一度、小児科を受診します
尿路感染症や肺炎などの病気が隠れていることがあるからです。
これらの病気は無症状だったり症状が不規則に出てきたりするので、発熱以外の症状に保護者は気付きにくいのです
なお、早産児は、免疫系の機能が十分に発達しておらず、感染症のリスクが高くなります

月齢ではなく医療機関を退院してから3ヶ月程度を目安に発熱に注意しよう!
早産児の感染症対策として母乳を飲ませるのはプラスになります
また、早産児はRSウイルス感染症の重症化リスクがあるため、抗体製剤を接種する必要があります
高熱への対応
熱は41度を超えると生命を脅かす危険性が高まるものの、高熱自体で脳に障害が起こったり後遺症が残ったりする可能性はほぼないと考えられています。
しかし、39度になったら小児科を受診して適切なケアを受けるのが良いでしょう
熱性痙攣

高熱による「熱生痙攣」、いわゆるひきつけを起こす場合があるよ!
生後3〜6か月ごろから5〜6歳くらいまでの子どもに見られ、起こす子の割合は5%くらいです
高熱が出てから24時間以内に発症する場合が多く、15分以内に症状が治れば大抵問題ありません

子どもが突然痙攣を起こすと狼狽えるけど、そのまま様子を見よう!
舌を噛まない様にタオルなどを子どもの口に入れようかと思う保護者もいますが、これは窒息させる可能性があり危険です
吐いた時は嘔吐物を気道に詰まらせない様に顔を横に向ける
痙攣発作がおさまったら一度、受診しておくと安心です。
昼間の場合は、かかりつけの小児科を受診します。
休日・夜間の場合、救急受診の必要性はケース・バイ・ケースです。
厚生労働省の相談事業である「こども医療でんわ#8000」で直ちに医療機関を受診した方が良いかどうかを相談するといいでしょう
発熱への対応の仕方
熱の出始めは体温が一気に上がり手足がすごく冷たくなるので温めてあげます
そして、熱が上がりきったら衣服は1枚少なめで過ごさせます

発熱時は多く着込んで汗をかいた方がいいと思っている保護者も見かけますが、脱水状態を促進することにつながるよ!
解熱剤の使用
特別な基礎疾患のない小児の場合、38.5度が解熱薬使用の目安と言われていますが、解熱剤の使用は「体調を整える」という視点で考えます
例えば、熱が高くて水分や食事が十分に取れない、夜眠れない、機嫌が悪いといった状態に子どもが置かれている様なら解熱剤使用の対象になります
服用のタイミング
熱は平熱まで下げる必要はありません
解熱剤を服用させるのは熱がある時だけ、頓用で用います
症状がひどくなければ1日3回などと定期的に服用させる必要はありません
解熱剤は、発熱の原因を治療する薬ではなく熱症状を緩和する対症療法薬
体温が何度以上になったら使いますかとよく聞かれますが、具合が悪ければ投与しますし、元気であれば投与しなくても良いのです
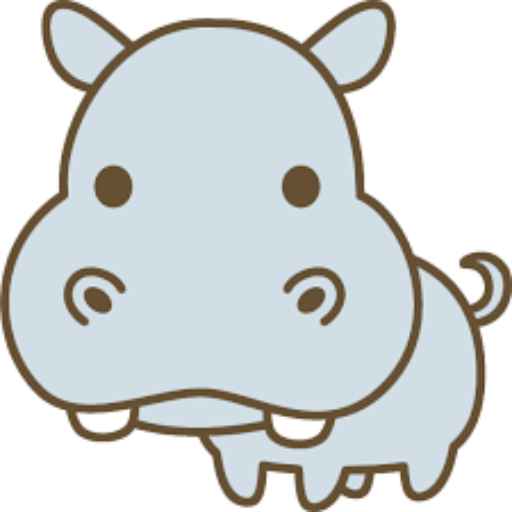
時間が来たからといって寝ているのに無理に起こして投与する必要もないよ!
薬の選び方
家にある成人の薬を子どもに飲ませようと思われる時があるかもしれませんが、小児は小さな成人ではありません。
薬の成分の吸収・代謝・排泄も成人と異なります
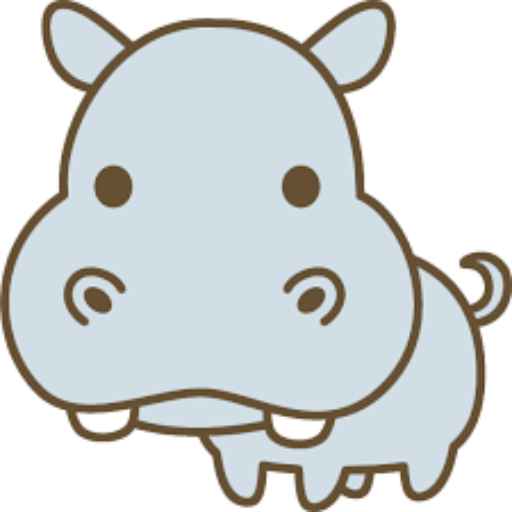
成人用と小児用の薬は内容成分が異なるので少量にして飲ませるなどのことはせずに小児用の医薬品を使用しよう!
基本的に乳幼児用に製造された薬であればどの商品を使っても問題ないと思います
ただし注意喚起していただきたいのは、解熱剤と風邪薬を同時に服用しない、ということ

過剰摂取になり、副作用が出る恐れがあるよ!
アセトアミノフェン
小児に用いる解熱薬としてはアセトアミノフェンという薬が推奨されます(世界的には、他にイブプロフェンという薬も使用します)
そのほかの薬は小児の解熱には使用しません
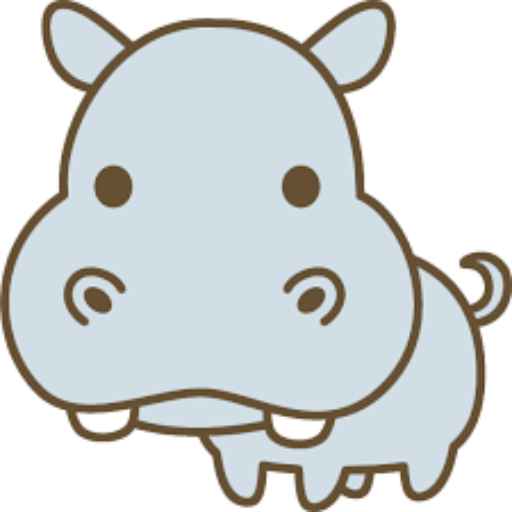
アセトアミノフェンは小児と妊婦への使用で最も安全とされる医薬品だよ!
アセトアミノフェンは投与後、1〜2時間で効果が発現します
解熱剤が効かない
また、保護者の中には「解熱剤を飲ませたのに平熱にならない」と心配する人が少なくありません。
体温が1度くらい下がれば解熱剤は十分に効いています
体温を一気に下げると、体が温度変化に対応できず、気持ちが悪くなったり、もう一度熱が出た時に強い寒気が起こったりするなどの弊害が生じることがあります
クーリング
残念ながら冷却シートで冷やすことにはそれほどの解熱効果はありません。
子どもが気持ちよさそうならやってあげるといいでしょう
脇の下など大きな血管が走っているところに氷枕などをタオルで包んだものを当てるのは効果がありますが、小さい子は嫌がることも多いので、あまり無理はしない様にしましょう
総合感冒薬
熱を下げるにはまず風邪薬を考えるのではないかと思います
実は「総合感冒薬」と記載されている医薬品には鼻水に効果のある抗ヒスタミン薬が含まれていることが多く、これは乳幼児に使用すると痙攣が誘発される場合もあることが知られています
小児の風邪薬・鎮咳去痰薬・鼻炎用内服薬には「2歳未満の乳幼児に使用する場合は、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること」との記載があるので注意が必要です
脱水予防
体温が一度上がるごとに不感蒸泄(皮膚や軌道から蒸散する水分)は10〜15%増えると言われているので、熱が出たら水分を多めに飲ませることが必要です
摂取する水分は、脱水によって不足する電解質を速やかに吸収できる経口補水液がおすすめです
この経口補水液を少量ずつ頻回に飲ませることが水分補給のポイントです
飲めるなら乳児も授乳の合間に少しずつ飲ませてあげてください
ただし、糖分を含んだ飲み物を頻繁に飲むのは虫歯につながるので発熱時以外は避けましょう


コメント